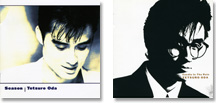 ─── 前回のお話を振り返ると、織田さん自身がそれまで抱いていたロックへの強いこだわりや美意識から、自分自身を解放して、音楽と素直に向かい合うようになった。その結果名盤『SEASON』が誕生し、そして翌年春『Candle In The Rain』が完成します。しかもそれまでのアルバムとは大きくその色合いが変わることになりました。今回はその1989年からお話を伺っていこうと思います。織田さんにとって、この2枚のアルバムは大きな意味を思っているのではないでしょうか? ─── 前回のお話を振り返ると、織田さん自身がそれまで抱いていたロックへの強いこだわりや美意識から、自分自身を解放して、音楽と素直に向かい合うようになった。その結果名盤『SEASON』が誕生し、そして翌年春『Candle In The Rain』が完成します。しかもそれまでのアルバムとは大きくその色合いが変わることになりました。今回はその1989年からお話を伺っていこうと思います。織田さんにとって、この2枚のアルバムは大きな意味を思っているのではないでしょうか?
織田 そうだね。俺にとって、とても意義深いアルバムだと思います。その意義を言葉にしようとすると、とても難しいけれど、自分のなかの「業」であったり、「トラウマ」であったり、そういうものに引きずられるだけで音楽をやってきたのが俺の20代だと思う。30歳になり『SEASON』、翌年『Candle In The Rain』という2枚のアルバムを作ることで、俺の中で何かが大きく変わった。自分自身のためにということで言えば、もう音楽を続ける必要がなくなったんだよね。この2枚のアルバムはそれまでの「自分」に対しての卒業証書的な意味があると思う。『Candle In The Rain』が完成したときに、実は「これが最後のアルバムかな」と思ったんだ。
─── 1989年8月MZA有明で4時間にもわたる大きなライブを開催しましたが、それには何か意味があったのですか?
織田 音楽を辞めるかもしれないなと思って、それまでレコーディングやライブで一緒にやってきた仲間たちに声を掛け、仲間やファンのみんなにありがとうの意味を込めてライブをやろうと考えました。それで当日参加できるミュージシャンを一同に介して、『WHY』のシングルだった「SHINE ON」から始めて、9th Image時代の曲、そして、織田哲郎としてソロデビューしてからの曲を発売順に演奏していったんだ。最後は『Candle In The Rain』の曲まで、バックもそれにあわせて交替しました。『WHY』の時代から『LIFE』までのギターは北島健二、それ以降は葉山たけしに代わり、というようにね。パーカッションの斎藤ノブさんにも後半参加してもらったんだけど、出番まで3時間ぐらい待たせちゃってね(笑)。4時間にもわたるライブのエンディングは参加ミュージシャン全員を呼んで、ベースやドラムがそれぞれ3人もいて、大騒ぎで締めくくったんだよ。
─── それで本当に音楽から引退しようと思ったのですか?
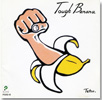 織田 思ったね。もう辞めていいやって感じだったね。いま思えば自分自身を救済する、いわば「治療」のために音楽をやっていたので、もう、その必要がなくなったとその時点では思っていました。辞めるにあたって、ふと考えたのは英語でガンガンロックを歌って、ギターを弾きまくるアルバムを作っていないなと思ってね。もともとロックギタリスト志望だったし、英語の歌の方が得意だったのに、プロになってからはその部分をほとんど封印してきたからね。こりゃあ最後に作っとかなきゃと思って『TOUGH BANANA』を作ったのよ。ロックで一番盛り上がれるメンバーを集めようと思って、ドラムは小田原豊(元レベッカ)、ベースは江川ほーじん(元爆風スランプ)、キーボードは小島良喜くん(元KUWATA BAND)という面子で、盛り上がりまくりでこのアルバムは作りました。 織田 思ったね。もう辞めていいやって感じだったね。いま思えば自分自身を救済する、いわば「治療」のために音楽をやっていたので、もう、その必要がなくなったとその時点では思っていました。辞めるにあたって、ふと考えたのは英語でガンガンロックを歌って、ギターを弾きまくるアルバムを作っていないなと思ってね。もともとロックギタリスト志望だったし、英語の歌の方が得意だったのに、プロになってからはその部分をほとんど封印してきたからね。こりゃあ最後に作っとかなきゃと思って『TOUGH BANANA』を作ったのよ。ロックで一番盛り上がれるメンバーを集めようと思って、ドラムは小田原豊(元レベッカ)、ベースは江川ほーじん(元爆風スランプ)、キーボードは小島良喜くん(元KUWATA BAND)という面子で、盛り上がりまくりでこのアルバムは作りました。
─── 『TOUGH BANANA』(タフ・バナナ)の作詞には、いまや第二次安倍内閣で厚生労働大臣に就任された舛添要一さんを起用されていますね。
織田 英語で詞が書ける人を探して、縁あって舛添さんにお願いしました。それが当初想像した以上にロックなイイ詞を書いてくれてね。舛添さんが元々ロックな人だったんだろうと思うよ(笑)
 ─── ちょうど同じ頃『いつかすべての扉が開かれる日まで』を作られますが、ジャケット写真といい、長く意味深なタイトルといい、英語を極端に排除した詞作りといい、当時「織田さんはどこへ行ってしまうんだろう? 音楽、辞めちゃうのかな?」と思った記憶があります。 ─── ちょうど同じ頃『いつかすべての扉が開かれる日まで』を作られますが、ジャケット写真といい、長く意味深なタイトルといい、英語を極端に排除した詞作りといい、当時「織田さんはどこへ行ってしまうんだろう? 音楽、辞めちゃうのかな?」と思った記憶があります。
織田 『Candle In The Rain』がそれまでの自分自身への卒業証書的な作品だったんだけど、このアルバムはある種「遺言」みたいなものだね。「これまでの自分はこういう人間でした。お世話になりました、ありがとうございます」という周囲の人への感謝の気持ちや「自分自身が美しいと感じることが出来る音楽はこういうものです」という最後のご挨拶状=遺言のような、そんな思いがあったね。当時の俺にとって『TOUGH BANANA』と『いつかすべての扉が開かれる日まで』この両極端な性格を持った2枚のアルバムを作ったことで、完全にスッキリした気分になったことは確かだね。
─── 音楽を辞めようとしても、仕事の依頼は多かったのでは?
織田 自分から進んで仕事関係の人に連絡することはせずに、時の流れに身を任せ、1年近くほとんど仕事をしなかった(笑)。その頃、雑誌に載っていた仙台のおすし屋さんの記事を読んで、「美味そうだな、よしっ、寿司食いに行こう」と一人で車に運転して仙台に行って(爆笑)そのまま予定も決めずに、秋田、日本海側を回って、四国へと一ヶ月ぐらい放浪したこともあったよ。とにかく散々プラプラしていました(笑)国内外問わず。今でも思うけど、一年の半分くらい放浪している暮らし、本当は俺にとって、そういう生活が理想だね(笑)。
─── 旅の話をもう少し詳しく聞かせてもらえますか。
織田 旅に出るとまずボーっとするね。最初の数日なんて、忙しい日常を引きずったままでしょう。頭が切り替わるまでにやっぱり2週間は掛かる(笑)。大抵いつも何の予定も決めず、のんびり過ごしてる。でも旅に出ると元気が出てくるから、計画的ではないけれど、行動的にはなるよ(笑)。車でプラプラしていたときは宿探しに困ってね(笑)。ちゃんとしたホテルは都会にしかないし、夜中にそろそろ疲れたし、ここら辺で寝たいな、と思っても民宿も営業時間外で受け付けてくれない(笑)。それでよく一人でラブホテルに泊まったよ(爆笑)。今はどうか知らないけど、空いているとね、一人でも案外泊めてくれるのよ、ラブホテルって。
─── 当時はお酒も普通に飲まれたと思いますが、旅先でお酒や食事にまつわる記憶はいかがですか?
織田 いろいろなところで酒蔵巡りをやったね。日本酒とくに地酒をよく飲み歩いた。やっぱり新潟のお酒は新潟で飲むと美味いねぇ(笑) あと記憶に残っているのは冬の富山で食べた鰤(ブリ)も美味かったなぁ(笑)。
─── そして、その後テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の主題歌の依頼が長戸さんから舞い込む。
織田 大幸さんには音楽を辞めるかもしれないという話はしていましたが、「まあイイから」とこんな俺の性格をよく理解してくれていてね。大幸さんはどんな仕事でも俺に振ってくるわけではなく、ここぞという時以外は放っておいてくれた。「ちびまる子ちゃん」の時は「こんな話があるんだけど、頼まれてくれない?」というオファーをいただきました。実はその頃自分の中では本気で音楽を世界から離れて、もう誰かのために曲を書くことはないと思っていました。ただその時に脳裏をよぎったのは娘のことだった。5月にフジテレビで放送された「Dのゲキジョー」でも話したけれど、娘が喜びそうなことをしておきたいと考えて、この仕事を引き受けることにしたんです。
─── それが空前の大ヒット、ミリオンセラーを記録します。『おどるポンポコリン』という曲にも相当インパクトがありましたが、実力派ブルースシンガーの近藤房之助さん、ソロシンガーとして活躍していた坪倉唯子さんがアニメの世界から飛び出したようなキャラに扮して登場したB.B.クィーンズもインパクトありましたね。
 織田 B.B.クィーンズのプロデュースやアイディア、戦略はすべて大幸さんが考えたものです。その大幸さんから依頼があって「ちびまる子ちゃん」用に当初2曲作っているんです。『おどるポンポコリン』と『ゆめいっぱい』という2曲を番組のオープニング用とエンディング用とセットで作曲・編曲し、オケの制作も担当することになりました。両極端な曲想だったけど、どちらもオケが出来上がるまでそれほど時間も掛からなかったし、楽しんであっという間に出来ました。 織田 B.B.クィーンズのプロデュースやアイディア、戦略はすべて大幸さんが考えたものです。その大幸さんから依頼があって「ちびまる子ちゃん」用に当初2曲作っているんです。『おどるポンポコリン』と『ゆめいっぱい』という2曲を番組のオープニング用とエンディング用とセットで作曲・編曲し、オケの制作も担当することになりました。両極端な曲想だったけど、どちらもオケが出来上がるまでそれほど時間も掛からなかったし、楽しんであっという間に出来ました。
─── 音楽ソフトを流通させるメディア(媒体)もアナログレコードからCDへとその比率が大きく移りかわる時代でもありました。この曲の大ヒットがそれを加速させたと分析する専門家も多い。
織田 本当にあれよあれよという間に大ヒット、しかもこの年(1990年)の最大のセールスを記録するヒットになった。そして年末にはレコード大賞受賞だよ(笑)驚いたね。
─── ところで肝心のお嬢さんの受けはいかがでしたか?
織田 微妙(笑)だったかな。それほど良かったわけでもなかった(笑)。
─── 音楽から事実上離れ、引退しようと考えていたにも関わらず、お嬢さんのためにと思って作った曲がレコード大賞とは、織田さんはやっぱり音楽とはトコトン縁があるということなのでしょうね。しかもこの年(1990年)、あるオーディションで相川七瀬さん(当時15歳)と出会うことになる。
織田 これも偶然が大きく作用している話でね。実は俺、オーディションの審査員の仕事なんてこれまで指折り数えられるほどしか受けていないのよ。たまたま気が向いたこともあり、暇だから引き受けてみようかと大阪に行ったそのオーディションで最初に現れたのが相川だったり、のちに札幌でたまたま引き受けたオーディションの審査員として出会ったのが大黒摩季だったり。俺はそういう巡り合わせにはなにかと恵まれているね。というか、これも運命なのかもしれないね。
─── 本当に引退してしまったら、さまざまな出会いや今日の相川さんも無かったかもしれない。
織田 そう思うと不思議だよね。自分でも1990年は本当に大きな転機だったと思うよ。もう音楽をやる必要がなくなったと思って、ずっと走り続けたのを止めた。でもずっと働き続けて、急に何もしなくなると、一年は途方もなく長く感じて、当時は凄いブランクだと思ったよ。ガンガン働いている時は1、2ヶ月休んだりしたら世の中からものすごく取り残される気がしてしまうよね。今では一年なんてあっという間に経ってしまうのに(爆笑)。
─── それは織田さんだけではないと思いますよ(笑)。
織田 齢を重ねると時の過ぎるのがとても早く感じるっていうのは、俺だけではないよね(爆笑)。
─── 一度は音楽から離れたものの、きっと世の中や音楽の神様が織田さんを必要としたんだと思います。
織田 『おどるポンポコリン』が大ヒットして、正直「まだ音楽を続けろ」と言われたようにも感じたし、何か見えない力に導かれるように音楽に戻っていったんだと思うよ。でも今こうして振り返ってみると、あの一年の空白があって、きっちり休んだことで、その後90年代の破壊力に繋がったのかもしれないと思っています。
─── ではその90年代以降のお話はまた次回と致しましょう。次回更新は9月12日(水)を予定しております。よろしくお願いします。
織田 了解。
 |