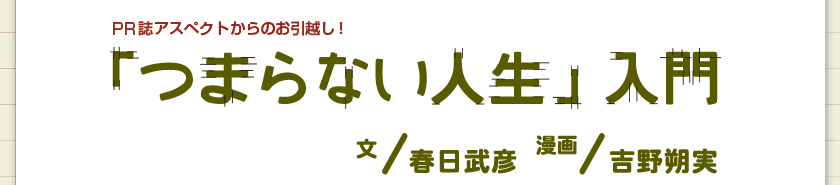トロリーバスとFのこと
ホルモンのせいに違いないが、中学三年になったらいきなり世の中が不調和に感じられるようになった。馴染みの風景からは親しみが失われ、輪郭ばかりがとげとげしく際立ってくる。世の中のすべてが「ぎくしゃく」して感じられ、足元にはいつも水枕を踏みつけているような感触があった。友人たちは、紙を切り抜いて作った二次元の存在に思える。
当時は新宿の戸山高校の近くに住んでいた。中三になった途端に引っ越したのだけれど転校するのも面倒だったから、新宿経由で電車通学をしていた。
あの時代には、明治通りをトロリーバスが運行していたのである。都電のように架線から電気を受けて、ゴムタイヤのバス(電気自動車)が走るわけで、車体は濁った緑色に塗られていた。モーターなのだから滑らかに走行するかと思えばそんなことはなく、運転手の動作を観察していたらしょっちゅうクラッチを踏んでいる。そのたびに立っている乗客は前に倒れそうになったり後ろにひっくり返りそうになる。実にぎこちない走りぶりだったのであった。
世の中のすべてに違和感を覚えていた中三のわたしにとって、このトロリーバスはまことに奇怪な乗り物に映った。屋根には二本のポールがあって、ときおり緑色の火花を散らせている。この昆虫みたいなポールが架線から外れたらバスは止まってしまうわけで、レールを走るのではないくせに架線から遠ざかる自由を持たない。リードに繋がれたまま散歩をしている犬のような存在である。そこのところが気に障った。どうしてこんな中途半端なものが大手を振ってメインストリートを走行しているのだろう。しかもバスの外観はあまりにも素っ気ない。緑一色に塗られているだけでラインも文字も入っていない。どこか不完全でしかも鈍重きわまりない。窓は妙に小さく、内部が薄暗い。陰気なのである。
毎日そんな陰気でぎこちない乗り物で通学することによって、わたしが捉えられている違和感はますます増強されていった。
一年に一回、学校では雑誌が発行された。《ほのお》という誌名だった筈である。その年に卒業する生徒たちの作文や詩で優れた作品を収録したり、学校行事の報告があったり、そんな雑誌であった。生徒たちの文芸作品のアンソロジー的な性格を備えていた。
友人のFと一緒に学校から歩いていた。大柄でハンサムで、零戦とかタイガー戦車などが好きな男だった。ミリタリー関係の記事を満載した『丸』という雑誌を毎号買っており、わたしはときたま彼からそれを借りていた。
そんなFが、いきなり《ほのお》のことを話題にした。今度の号には、オレの作文が載るんだよと自信満々に断言するのである。なぜなら先日書いた作文を担任が「秀でている」と絶賛していたから、と。
ミリタリー少年の筈だったFが唐突にそんなことを言い出したのでわたしは困惑した。そもそも彼は作文の出来栄えなどどうでも良いと思うタイプであったし、『丸』は読んでも《ほのお》なんて無関心だとばかり思っていた。自分の作文が載ることになっていると強調する態度が、俗っぽい価値観に汚染されたというか、彼らしからぬ様子だと感じられて鼻白んだ。「お前、変わったな」と言いたくなったが、そんなことを口にするのは寂しいことだと思い直して我慢した。
半年以上経ってから《ほのお》が発行され、しかしFの作文は載っていなかった。わたしは「ざまあみろ」と思った。同誌にわたし自身の作文は収録されていなかったものの、表紙の絵は当方が描いたもので、これは美術の時間に描いた作品であった。断面図みたいな絵で、人間を黒いシルエットで表現した奇異な作品であったが、大人には新鮮に見えたのかもしれない。
Fとは進学する高校が違ったし、わたしの家はまたしても引っ越したので、卒業以来彼との縁は切れた。
鼻をほじる
精神科医になりたての頃だから、もう四半世紀近く昔のことである。大学病院では教授が診察をするときには、新入医局員がそこへ陪席する。そうやって教授と患者との「やりとり」を眺め、それを手本とする。
陪席しながら医局員たちは自分なりに見立てをつけ、診断を考え、またどんな薬を処方するかを予測する。診察を終えた後で教授が説明をしてくれ、あるいは医局員へ質問を与えることで臨床を学んでいくわけである。
ある日、診察後の教授と医局員とのディスカッションが終わり、新入医局員は全員が退室した。だがわたしだけ何かの用があって引き返し、診察室にいた教授に話し掛けた。すると一人で部屋に残っていた教授は、椅子に腰掛けたまま、鼻の穴をほじりながらわたしに応対をした。わたしは立っていたので、教授を眺め下ろす形になる。彼は白衣をきて足を組み、人差し指を鼻へ突っ込みながら受け答えをしていた。
わたしは当惑した。一瞬、当方を馬鹿にする仕草かと思ったがそういった意思表示ではなさそうであった。たんに鼻をほじりたかったからそうしていただけとしか見えなかった。だがそんなことを医局員の前でするものだろうか。あまりにも無防備というか無頓着ではあるまいか。羞恥心を見せるでもなく、「うっかりして」といった感触もまったくなかった。異様というか強烈な違和感がわたしを襲った。
真っ白で糊の利いた白衣を着た教授が、人前で足を組んだまま鼻の穴をほじっている――これは行儀が悪いとか、傍若無人といったこととは次元が違うように思えた。わたしは事態をまったく理解できなかった。シュールな冗談としか思えなかった。
今になって思い返しても、あの光景は何だったのだろうと首を捻らざるを得ない。大げさな表現に聞こえるかもしれないが、両親の性交を目撃してしまった幼児さながらの衝撃をわたしは覚えたのであった。もちろん衝撃は時間が経てば徐々に収まって来るけれど、あれはいまだに得体の知れぬ違和感としてわたしの頭の中に居座り続けている光景なのである。
どこかおかしい
モナ・リザ、あの絵ほど贋作やパロディーの多い作品はないだろう。そしてどれもこれも贋物は一目で分かる。まぎれもなく、安っぽいのである。
正式に美術館から許可を得て、日本人画家が時間をかけてじっくりとモナ・リザを模写して、その完成したものを雑誌で見たことがあった。
オリジナルと瓜二つの出来映えかと思ったら、そんなことはなかった。明らかに違う。だがどこが違うかを言葉では指摘できない。おそらく口もとが問題で、身も蓋もない言い方をするなら、模写のほうが微妙に下品なのである。それに絵の印象が、全体として模写の方がどことなく「鋭角的」な印象がある。
ものすごく微妙な差異が大きく雰囲気を変えてしまうそのデリケートさに、モナ・リザの価値があるのだろう。ことに微笑といったものは、想像以上に精妙な造形要素から成り立っているに違いない。
初診で、うつ病の中年女性と会った。彼女がモナ・リザに似ていたというわけではない。むしろダリの女房に似ていた。表情は暗く沈み、問診からうつ病は間違いないと思われた。
だが、何か気になるところがあった。彼女に対してどこか違和感を覚えたのだけれど、その原因が分からない。もどかしいが、はっきりしない。あたかも彼女の替え玉と面接をしているかのようなおかしな気分であった。
しばらくして、気が付いた。
彼女は歯が異様に白かったのである。半透明の輝くような白さの歯で、それがどうも不自然というか人工的なのである。入れ歯であってもあそこまで白くは作らないのでないか。歯科で歯を白くするケアを受けると、本物の歯なのにあんな突飛な白さになるのかもしれない。いずれにせよ、俯き加減で表情の乏しい彼女はあまり歯を見せない。だがちらちら見える歯の奇妙な白さ(それは美と健康のカリカチュアのようであった)が、違和感を作り上げていたということなのであった。
彼女が心臓発作とかそんな原因で急死したとする。生気を失った顔を眺めると、半分開いた口からびっくりするほど白い歯が誇らしげに光っているだろう。そのちぐはぐな印象に、絶句してしまう人は多いのではないか。
ある日、彼女がメガネを
大学に通っていたとき、わたしと同世代のある女性が、次第に精神を患っていくその途中経過を目撃した。今にして思うと、たぶん統合失調症だったのではないか。
生活態度が急にルーズになってきた。本来の彼女には似つかわしくないのである。どうしちゃったのかなあと思っていたら、近眼になったと言い始めた。ああそう、と適当に受け流していたら、ある日、まるでお爺さんが使うような古めかしい眼鏡を掛けてきた。わたしは呆然とするしかなかった。もちろん彼女にはまったく似合わないし、レンズの度があっているとも思えない。箪笥の奥から出てきたので、などと意味不明のことを言う。とんちんかんな眼鏡を掛けた彼女は、絶望的な違和感を発散していた。
「好ましいもの」と「暴力的なもの」
中二までは杉並に住んでいた。ちょうど昭和三十年代の最後の時期に重なる。
定期試験が終わると、歩いて方南町へ行った。環七通りの交差点の近くに模型屋があって、そこで鉄道模型を眺めるのが楽しみだったのである。
この方南町の交差点のあたりは、妙にモダンというかアメリカめいた雰囲気があった。喫茶店とかビルのたたずまいとか看板などが、広々とした印象と相俟って、日本的貧乏臭さから隔絶していた。流線型の車が走り回る豊かな先進国としてのアメリカをなぜか彷彿とさせた。この印象は中学生のわたしが勝手に抱いていただけかと思っていたら、小林信彦のエッセイにやはりこの場所がアメリカっぽいといったことが書かれていたことを記憶している。
そんな次第で、アメリカめいた空気を体感すると同時に模型屋で楽しいひとときを過ごすという意味でも、少々遠いけれども方南町まで足を運ぶのはささやかな喜びなのであった(そういえば模型屋に飾られていた機関車や貨車には、輸出用の米国型車両が多く含まれていたのだった)。
交差点に行き着くまでに、わざと脇道へ入って退屈な住宅街をうろついたりもした。そのほうが、交差点のあのアメリカっぽさをより現実離れしたものとして味わうことができる。
家々が立ち並ぶ細い道を歩いていたら、いきなり変電所が出現した。家一件の敷地に相当する広さが金網で囲われ、その真ん中にどっしりとトランスだのコイルだのが鎮座し、太い電線と白い碍子がいかにも高圧電流の危険さを誇示している。金網の内側には電磁波が同心円状に広がっているような気がする。
小規模ながらも変電所が、文化住宅と隣り合わせに存在していることにわたしは驚かされた。どうも危険な気がしてならない。こんな具合に住宅地の中に変電所があるのは、喩えて言うなら、酪農の牛舎を覗いたら仕切りのひとつに虎が眠っていたようなものであろうか。まことに違和感に満ちている。
最近自動車を買ったので、四十数年ぶりに環七経由で方南町の交差点に行ってみた(わたしは最初から免許を持っていないので、妻の運転である)。残念なことに、「憧れの」アメリカを連想させるマジックは雲散霧消していた。では変電所の方はどうなったのか。そこまで確かめる元気は、もはやなかった。
喜びの予兆が訪れる
風邪薬の箱に印刷してある効能書きを見ていたら、咳とか痰とか熱とか悪寒とか「くしゃみ」とか鼻水とか関節痛などに加えて、《全身違和感》と記してあった。たしかに風邪をひくと自分の身体なのに自分の領分ではなくなってしまったような奇妙な気分を覚える。それまでの自分に比べて、明らかに不自然な自分自身を体感する。
ただしわたしはこの全身違和感が嫌いでない。もちろん翌日にキツイ仕事や当直が控えていないという前提での話であるが。
だるさや発熱と一緒に訪れるこの違和感は、なるほど不都合な部類に入るだろう。肉体の動きを鈍らせ、感覚を狂わせる。だが不快であることとは微妙に異なる。いや、むしろ屈折した快感に近いかも知れない。どことなく「やるせない」気分を漂わせ、よるべなさを醸し出す。よそよそしさを現実から受けてしまうと同時に、ノスタルジーにも似た孤独感がうっすらと湧き起こる。
風邪をひいて昼間からベッドに横たわっていられたら、これはもう最高の体験である。うつらうつらしながらラジオを小さな音で点けっぱなしにしていると、球根の植え方だの俳優の思い出話だの陳腐な歌謡曲などが途切れ途切れに耳に届く。時計を見るのも億劫なので今が何時か分からぬまま、またしても泥のような眠りに落ちている。記憶の断片が脈絡なく脳裏を横切る。窓の外からは、ときおり自動車のエンジン音や物売りのスピーカー音が聞こえる。
当たり前の日常が、遠くもあり近くもあるように感じられる。日々の退屈な営みが、懐かしく思えてくる。たぶん明日には回復しているだろう。そう考えると、この全身に行き渡っている違和感が、ある種の救いであるかのようにも思えてくる。辛さと一緒に、ほんのりと喜びの予兆が訪れているかのようだ。
わたしにとって《全身違和感》は、無愛想で気まぐれなくせにバースデーカードだけは必ずくれる友人みたいなものである。